農・人・くらし
NPO法人 農と人とくらし研究センター コラム
米のことあれこれ-米缶の話-
お蔵の管理は義母がしていたので、あまりその頃のことはわかりませんが、稲の刈り取りが終わり、脱穀する頃になると、天気のよい日にお蔵から米缶を出して、陽に当てていました。そのころはこんな風景をあちこちで見かけました。
そのころ、籾摺りは隣の家と仲間でやっていましたので、籾摺り機から新米が出てくると、1斗ずつ枡で量って竹箕に入れ、義父や家人、隣のおじさんが交代でブリキ缶の中に納めました。
やがて、コンバインで収穫する家が増えてきて、組(集落)の共有物であった籾摺り機も使わなくなり、わが家もJA出荷分はJAのコンバインで刈り取り、そのままライスカントリーへ出してしまい、伝票が戻ってくるだけになりました。自家用分は義母の縁戚のおじさんにコンバインで刈ってもらい、そのままそこで乾燥機にかけ、紙袋に入って新米が届くようになりました。それをブリキ缶に入れるのは家人一人の仕事になってしまい、高い缶の口まで30㎏の米袋を持ち上げて入れることに往生した家人は、米専用冷蔵庫をカタログに見つけ、さっさと買い入れたのでした。おじさんの所からきた30kg入りの米を積んだトラックは、冷蔵庫前まで乗り付け、次々に冷蔵庫へ運び入れてしまえばもうおしまいです。
米900㎏用の冷蔵庫は、秋には米で一杯になりますが、食べるにつれて少しずつ減っていき、春には空いた部分に干ししいたけや切干大根の入った袋が詰まり、夏には格好の冷蔵庫になって、漬物、収穫した野菜、スイカ、ぶどう、チョコレートなどの菓子、様々な飲み物のペットボトルなどが占拠して、米は片隅に追いやられています。
この冷蔵庫、冬には外気のほうが低いので(北海道ほどではありませんが)あまり電気も使わないようですが、夏には台所にある冷蔵庫よりも庫内温度が低いので、物の保管には本当に重宝しています。家人は自分でも様々なものを入れるくせに、人に向かっては「これは米の冷蔵庫やで、他のものを入れるな」と、時々申されます。
この冷蔵庫の一番ありがたいことは、精米する時に、扉をあけ30㎏の玄米1袋を取り出し、車に積んでコイン精米にさっと持っていけることです。以前、ブリキの米缶のときは、義母が缶の下の取り出し口から1斗枡で量り、竹箕に取り出したものを、この頃は、コイン精米などなかったので、土間に備え付けの隣家と共同の精米機に入れ、半日ほどかけて精米していたものでした。冷蔵庫を入れた頃に、義母もこの精米が面倒になったのか、いつの間に精米機を隣家に譲ってしまい、今ではJAにあるコイン精米機に私が車で乗りつけることになりました。
ところで、月に2回通っている古文書研究会では、海津郡の豪農「片野家年内勝手方所事取斗覚」という古文書を読み下しているのですが、先日、三月の項に次のような文がありました。 「貯え置き候飯米当月中残らず俵〆置きさすべき事」
この文が意味するところを、80歳位くらいに思われる会員の女性が皆に解説してくださいました。昔は収穫した米を入れた俵が、半年ほどたった3月頃に緩んできて、それはまた暖かくなる頃で、虫も入るようになるから、この時期に俵を〆直したということでした。それにあわせて同年輩の方々が昔を思い出す話を次々にされていましたが、その中にこんな話。
「米を俵でとっとくことはほんとにえらいことやったな、ブリキの米の缶はできた時は、なんとええもんができたやろと思って、嬉しかったわな」
わが家はブリキの缶に往生して、冷蔵庫を買ったのでしたが、そのブリキの米缶が人々の喜びと期待を持って取り入れられた時代があったのだと、思わされたできごとでした。
『ひぐらし記』No.18 2007.11.20 福田美津枝・発行 より転載
PR
内戦の地にも人々の暮らしがある(下)
研修生たちはその後も研修を続け、全員無事に2ヶ月半にわたる研修を修了した。最終日の11月9日、JICA東京でコース全体の評価会がもたれ、私は研修生とともにその席につく機会をもった。このとき、バリさんは、日本で多くのことを学んだが、自分にとって最も印象深かったのは、岡谷での環境点検のとき、射撃場の跡地で区長さんが語った言葉だった、とふりかえった。鉛の弾が埋まった跡地利用について、土壌の鉛汚染を孫の代に残さない処置を考えている、と区長さんは説明した。自分たちさえ良ければいいのではなく、次の世代のことまで考えていることに、バリさんは衝撃を受けたという。
 アフガニスタンが今どんな状況に置かれているのか、私には想像することすら難しい。研修の最後の数日間、研修生は帰国後に実践するという想定の「生活改善活動計画」をそれぞれ立てることが課せられていて、私は何人かを手助けする役目を引きうけた。その中にアフガニスタンからのもう一人の研修生のバレゾさんがいた。活動対象に彼女が選んだのは、FCDC(女性コミュニティ開発委員会)という村の女性リーダーたちの組織である。彼女が描いたプロブレムツリー(問題分析系図)は、女性たちが置かれた困難な状態を反映して、延々とどこまでも続いていた。村のFCDCのメンバーは、定期的な会合を自分たちではもたない → 開発委員会の目的も会合の目的も知らない → 会合で自分の意見を言わない → 社会活動家に依存している → 自発性に欠ける → 問題を見極める機会がない……。
アフガニスタンが今どんな状況に置かれているのか、私には想像することすら難しい。研修の最後の数日間、研修生は帰国後に実践するという想定の「生活改善活動計画」をそれぞれ立てることが課せられていて、私は何人かを手助けする役目を引きうけた。その中にアフガニスタンからのもう一人の研修生のバレゾさんがいた。活動対象に彼女が選んだのは、FCDC(女性コミュニティ開発委員会)という村の女性リーダーたちの組織である。彼女が描いたプロブレムツリー(問題分析系図)は、女性たちが置かれた困難な状態を反映して、延々とどこまでも続いていた。村のFCDCのメンバーは、定期的な会合を自分たちではもたない → 開発委員会の目的も会合の目的も知らない → 会合で自分の意見を言わない → 社会活動家に依存している → 自発性に欠ける → 問題を見極める機会がない……。
内戦の地にも人々の生活がある。戦争状態が何年も続き、今をいかに生き延びることだけを考え、将来を思うことすら儘ならない人々がいる。そんな過酷な状態だからこそ、「明るい」将来のビジョンを描くのは容易でないと同時に何よりも必要なことなのだろう。アフガニスタンからの研修生の言葉を、私はそのように聞き取った。
片倉和人
内戦の地にも人々の生活がある。戦争状態が何年も続き、今をいかに生き延びることだけを考え、将来を思うことすら儘ならない人々がいる。そんな過酷な状態だからこそ、「明るい」将来のビジョンを描くのは容易でないと同時に何よりも必要なことなのだろう。アフガニスタンからの研修生の言葉を、私はそのように聞き取った。
片倉和人
内戦の地にも人々の暮らしがある(中)
JICA(国際協力機構)の研修生を初めて岡谷の農と人とくらし研究センターに迎えて「構想づくりワークショップ」と銘打った3日間の研修を行った(2007年10月18日~20日)。(社)農山漁村女性・生活活動支援協会がJICAから委託を受けて実施する「農村女性能力向上」コースの研修生で、生活改善アプローチを日本で学んで帰国後に自国で取り組むことを目標としている。今年は、カメルーン、チャド、ニジェール、タンザニア、イエメン、アフガニスタン、インド、スリランカ、フィジー、メキシコの10カ国から11人(女性9人、男性2人)が参加していた。
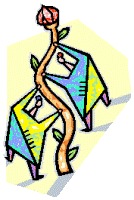 農村開発にたずさわる研修生たちに考えてもらいたかったのは、将来についてのビジョンをもつことの大切さである。その日暮らしの貧しい人たちは、お金や仕事がないだけでなく、将来になんら夢や希望をもっていない場合が多い。そういう人たちに対して、お金や仕事を与える援助ではなく、将来について自分のビジョンをもつことを手助けするような支援ができないか、その方法を伝えたいと思った。
農村開発にたずさわる研修生たちに考えてもらいたかったのは、将来についてのビジョンをもつことの大切さである。その日暮らしの貧しい人たちは、お金や仕事がないだけでなく、将来になんら夢や希望をもっていない場合が多い。そういう人たちに対して、お金や仕事を与える援助ではなく、将来について自分のビジョンをもつことを手助けするような支援ができないか、その方法を伝えたいと思った。
「参加型農村調査から構想づくりへ」をテーマにしたワークショップのプログラムを用意した。1日目の午後は皆で地元の地区を歩いて生活環境点検を行い、宝(良い点)とチャレンジ(問題点)を探し、参加者自らデータを収集する。二つの班に分かれて、2日目はそれを地図に落し込み、課題と「モッタイナイ」資源をリストアップする。その上でこの地区の将来の構想図(ビジョン)を1枚の大きな紙に描く。3日目は、課題の解決もしくはビジョンの実現をはかるプロセスを考える。班ごとに1つのテーマを決め、女性グループを育成して課題にとりくむという筋書きの寸劇を作って演じる。
プログラムは順調に進み、研修生は笑顔で岡谷を後にした。思い通りに実施できたのは、多くの方の助けを借りてのことだった。環境点検の案内役をお願いした区長の山之内寛さん、ボランティアで参加いただいた諏訪農業改良普及センターの林邦子さん、岐阜県から馳せ参じてくださった福田美津枝さん、それに休みをとって手伝ってくれた姉と妻、3日間を通じて世話をやいてくれた父母、JICA研修コーディネーターの栗田理恵さん、農山漁村女性・生活活動支援協会の担当者兼講師の富澤ひとみさんと古田由美子さん、こうした方々が一つのチームとなって、ファシリテーター(進行役)の私を支えてくれた。
ワークショップの最後は、短くてもふりかえりの時間をとって、参加者全員に感想を述べてもらうことにしている。岡谷での3日間をふりかえり、「将来に対して明るいイメージをもつことが大切だとわかった」と研修生のひとりが感想を述べた。そう語ったのは、最年少の20代男性、アフガニスタンからの研修生のバリさんだった。ビジョンを持つことの大切さを伝えたいと思ったが、ビジョンの中身は人それぞれで、内容まで特に深く考えていなかった。「明るい」という形容詞が、私の心に小さな棘のように引っかかった。
片倉和人
「参加型農村調査から構想づくりへ」をテーマにしたワークショップのプログラムを用意した。1日目の午後は皆で地元の地区を歩いて生活環境点検を行い、宝(良い点)とチャレンジ(問題点)を探し、参加者自らデータを収集する。二つの班に分かれて、2日目はそれを地図に落し込み、課題と「モッタイナイ」資源をリストアップする。その上でこの地区の将来の構想図(ビジョン)を1枚の大きな紙に描く。3日目は、課題の解決もしくはビジョンの実現をはかるプロセスを考える。班ごとに1つのテーマを決め、女性グループを育成して課題にとりくむという筋書きの寸劇を作って演じる。
プログラムは順調に進み、研修生は笑顔で岡谷を後にした。思い通りに実施できたのは、多くの方の助けを借りてのことだった。環境点検の案内役をお願いした区長の山之内寛さん、ボランティアで参加いただいた諏訪農業改良普及センターの林邦子さん、岐阜県から馳せ参じてくださった福田美津枝さん、それに休みをとって手伝ってくれた姉と妻、3日間を通じて世話をやいてくれた父母、JICA研修コーディネーターの栗田理恵さん、農山漁村女性・生活活動支援協会の担当者兼講師の富澤ひとみさんと古田由美子さん、こうした方々が一つのチームとなって、ファシリテーター(進行役)の私を支えてくれた。
ワークショップの最後は、短くてもふりかえりの時間をとって、参加者全員に感想を述べてもらうことにしている。岡谷での3日間をふりかえり、「将来に対して明るいイメージをもつことが大切だとわかった」と研修生のひとりが感想を述べた。そう語ったのは、最年少の20代男性、アフガニスタンからの研修生のバリさんだった。ビジョンを持つことの大切さを伝えたいと思ったが、ビジョンの中身は人それぞれで、内容まで特に深く考えていなかった。「明るい」という形容詞が、私の心に小さな棘のように引っかかった。
片倉和人
内戦の地にも人々の暮らしがある(上)
PARCスリランカ報告会に岡谷から駆けつけた。2007年10月5日、東京広尾のJICA地球ひろばにおいて、「スリランカ内戦の現状と今後の展望」と「ジャフナ漁村の人々の暮らしとプロジェクト報告」と題する講演があった。報告者は、アジア太平洋資料センター(PARC)共同代表の中村尚司さんと井上礼子さん。PARCは、少数民族タミル人の住むジャフナ半島で、漁村の人々の自立と持続的な発展を支援する民際協力を行っている。最近ジャフナを訪れた帰国報告だったが、2007年4月29日深夜、スリランカのコロンボに滞在していた中村さんは、LTTE(タミル・イーラム開放のトラ)空軍機によるコロンボ空襲をホテルの部屋から目撃したという。
井上さんの報告によれば、1980年代から続く内戦で、ジャフナ半島では、多数民族シンハラ人の政府軍による攻撃を受け、タミル人の漁民たちは家を失い難民となった。そうした難民たちが、2002年の停戦合意後、海岸に家を建てて生活の再建を始めていて、PARCは2004年5月にジャフナに事務所を設置して、彼らの生活支援に着手した。
 まず、乾燥魚加工を始めるべく、2004年12月インドネシアに乾燥魚技術研修に行く。その直後12月24日、スマトラ沖地震の津波が襲い、難民の家は跡形もなく流される。PARCは津波緊急援助で住宅の再建を支援、一日も早い漁の再開と従来の生活への復帰をめざす漁民に対して、地引網のための網と船を提供、被災した女性たちには乾燥魚加工の支援を開始する。しかし、2006年8月内戦が再燃、ジャフナは陸の孤島と化し、軍は漁民たちに漁も海岸に近づくことも禁止する。食糧にもことかく漁民に、PARCは紅茶、砂糖、スパイス、粉ミルク、さかな缶詰などを送る緊急食糧救援を行い、さらに漁に出られない彼らのために養鶏のプロジェクトを開始する。
まず、乾燥魚加工を始めるべく、2004年12月インドネシアに乾燥魚技術研修に行く。その直後12月24日、スマトラ沖地震の津波が襲い、難民の家は跡形もなく流される。PARCは津波緊急援助で住宅の再建を支援、一日も早い漁の再開と従来の生活への復帰をめざす漁民に対して、地引網のための網と船を提供、被災した女性たちには乾燥魚加工の支援を開始する。しかし、2006年8月内戦が再燃、ジャフナは陸の孤島と化し、軍は漁民たちに漁も海岸に近づくことも禁止する。食糧にもことかく漁民に、PARCは紅茶、砂糖、スパイス、粉ミルク、さかな缶詰などを送る緊急食糧救援を行い、さらに漁に出られない彼らのために養鶏のプロジェクトを開始する。
平和時の生活改善の取り組みしか知らない私には、PARCのプロジェクトの困難さは、ちょっと想像を越えていた。講演後の意見交換で、「平和構築を待っていられない。紛争地域でも、生活支援の取り組みを、できることはやる」と、スリランカと関わりの深い参加者のひとりが発言していた。内戦地域にも生活があり、そこには生活改善を必要とする人がいる。戦争状態だから、支援活動をしなくていい、という訳にはいかない。そういう趣旨の発言だった。
もっと詳しい話を聞きたいと思ったが、近々岡谷でJICA研修の受け入れを控えていて、準備の心配があったので、交流会には参加しないでその日は報告と意見交換だけ聞いて帰った。
片倉和人
井上さんの報告によれば、1980年代から続く内戦で、ジャフナ半島では、多数民族シンハラ人の政府軍による攻撃を受け、タミル人の漁民たちは家を失い難民となった。そうした難民たちが、2002年の停戦合意後、海岸に家を建てて生活の再建を始めていて、PARCは2004年5月にジャフナに事務所を設置して、彼らの生活支援に着手した。
平和時の生活改善の取り組みしか知らない私には、PARCのプロジェクトの困難さは、ちょっと想像を越えていた。講演後の意見交換で、「平和構築を待っていられない。紛争地域でも、生活支援の取り組みを、できることはやる」と、スリランカと関わりの深い参加者のひとりが発言していた。内戦地域にも生活があり、そこには生活改善を必要とする人がいる。戦争状態だから、支援活動をしなくていい、という訳にはいかない。そういう趣旨の発言だった。
もっと詳しい話を聞きたいと思ったが、近々岡谷でJICA研修の受け入れを控えていて、準備の心配があったので、交流会には参加しないでその日は報告と意見交換だけ聞いて帰った。
片倉和人
若きセールスマンの芋ほり
いよいよ芋ほりを始めました。10月中ごろの月曜日と、翌週の月曜日の2日で、2人で掘りあげました。1株に大きな芋が2つくらいついていたが、あとは小さな芋ばかりと、期待はずれの量にがっかりして、その大きな芋も何かにかじられた跡があるといってがっかり。「おばさん、物を作るって難しいね、もっとええもんができると思った」とか、「フクちゃん、来年はもっとようけ(たくさん)できるように研究しなあかん、肥料が足りんのやないか、途中で肥料をやったほうがええんやないか、研究せい」とか、昼ご飯を食べながら話します。
(この日の昼ごはんは、掘り取った芋を使って、さつま芋のフルコースを作りました。さつま芋ご飯にさつま芋と蕪の葉の味噌汁、大学芋、さつま芋と蕪の葉入りオムレツ。息子は、「何や、また芋ばっかりか」とうんざりしていましたが、Mくんは、「おばさん、すごい!さつま芋ばっかでこんなご馳走ができるんや!」と喜んでくれました。お愛想半分としても、作り甲斐、食べさせ甲斐のある、好ましいM君)
「M君、芋ほり大会やらへんの?」と聞くと、「おばさん、やりたかったんやけど、よう考えたら僕、月曜が休みやで、そんな日に来てくれる子供おらへん」。確かに、彼は営業マンなので、土・日は稼ぎ時なのでした。
掘った芋は「おばさんとこの畑で作った芋やで、おばさんとこで食べて」と、大半を置いていきました。見ると、確かに大きな芋もかなりありましたが、小さな小さな、小指ほどの芋まで、丁寧に掘り取ってきていました。良さそうな芋は友人・知人に分けたり、その頃、地元の正眼短期大学ボランティア活動で、ブラジル人学校の子供たちにそば打ちとおやつ作りをすることになっていたので、鬼まん(さつま芋の入った蒸し菓子)を作ることにして、そのさつま芋を使いました。
それでもまだたくさん残っているので、どこかで売って、せめて苗代だけでも戻してあげようかとも思いましたが、彼らは「ゴルフやゲームやること思えば、そんな金、大したことない」などというので、では、その働きが無駄にならないよう、おいしく食べることにしました。小さな小さなさつま芋は、丁寧に洗って、さつま芋ご飯や芋粥、豚汁などに使いました。そのほかに大学芋や、バター煮にして食卓に出し、あとは、凍みないようにさや糠(籾殻)を入れた紙袋に入れて、納屋の暖かいところにおきました。
不肖の息子は、M君に引きずられての芋作りでしたが、M君は、期待ほどの成果が得られなかった芋作りにもめげず、来年もやる気です。「畑がまだ余まっとるで、春先にじゃが芋でも植えたら?」と誘うと、「ほんと、おばさん、春も使わせてもらってもええの?フクちゃん、そしたら今度はじゃが芋作りや」と張り切りだしました。うちの空き畑でM君が畑仕事を愉しみ、百姓嫌いな息子に畑仕事をさせてくれればと、オジサンとオバサンは期待しながら応援しています。
『ひぐらし記』No.18 2007.11.20 福田美津枝・発行 より転載
暮らしの智恵の煮込みうどん
そんな日に、遠くへ出かけることになり、夕飯を先に食べてもらうようにと、そして「煮込みうどんをしてもいいよ、アブラゲもかしわもあるから」と母に頼んで出かけました。
母の作る煮込みうどんは、油揚げやかしわ、ねぎを入れたしょうゆ味の汁の中に、乾麺をそのまま入れて煮込むものです。在所では一度乾麺を別にゆでておいてから、煮込み汁の中に入れて煮込んでいましたので、最初はこの煮込みうどんにびっくりしました。
しかし麺をゆでる手間が省け、ゆで汁も別に悪いものではない、そしてとろみのある汁が、のっぺい汁での片栗粉の役目のように、冷ましにくくする保温にもなるのだとわかって、百姓仕事に忙しかった暮らしの智恵であると感心しました。
その夜遅く帰ってきてお勝手を見たら、ガスコンロの上にねぎがたくさん入った煮込みうどんの鍋がありました。
福田美津枝『日々の暮らし・日々の食べもの 21』より転載
学ぶことの楽しさ…古文書研究会
退職した昨年は、県下5ヵ所であるこの講習会に3ヵ所出席して学びましたが、それでも難しく、腹立ち紛れに「初心者にわかりやすく教えてください、初心者向け講習会がこんなに難しくてはついていけません」とアンケートに書いて出してきました。
5ヶ月ほどたった2月初め、この協会から電話がありました。「昨夏の講習会の時のアンケートで、難しかったという声を何人かから聞いたが、もしよかったら、毎月2回行っている研究会に参加して、古文書を読み解く気はありませんか、第2と4火曜日の午前と午後の2回に分けて研究会を開いています。参加されるようなら午前か午後かを決めてお電話ください。これはアンケートに難しかったと書いてあった人で、住所や電話番号、名前を書いてあった人に呼びかけています」という丁寧なお誘いの電話でした。
これはありがたいと思い、頭のすっきりしている午前に決め、電話でお願いして、参加することにしました。
研究会は30人くらいのメンバーでした。岐阜市にある未来会館の小さな階段教室が会場でした。先生が1人おられ、テキストを用意されて、それを先生と一緒に読み解いていくものです。先生が読んでいきながら、白板にマーカーで読み方を書いていきます。時々、会員から違う読み方が出されると、皆で議論し合い、結論を出していきます。最初はまったく読めずに、ひたすら先生の読み方を聞き、板書を写すだけでしたが、このごろはどうにか自分でも読み進むことができ、先生の読み方や板書で確認するというように進歩してきました。
板書を写すといっても、階段教室の前の方からもう席が決まっていて、いくら早く会場についても、前の席をとることができません(別に決めてある訳ではないのですが、決まっているので)。新参者は一番後ろの席なので、マーカーの古びたものを使われると薄くて、板書もわからないことがありましたが、お世話役の方が清書したものを次回にプリントして配布されるので、それで復習することができます。
メンバーは男性7に女性3という割合で、ずいぶんお年の方ばかりです。電話を貰って、私と同時に参加した人が他に2人ありました。その3人は最初に参加した時に自己紹介をさせられました。私は「食文化に興味があり、そういう古文書を自分で読み、その時代の食べ物をことを知りたい」と申し上げたところ、何回か後の研究会のテキストに「片野家年内勝手方諸事取斗覚」という古文書が用意され、「食文化を研究される方があるので、この古文書を用意しました」と説明されました。恐縮しつつも嬉しく、しかし他の皆さんが満足されるかと思うと不安にもなりました。
研究会は2時間で、前半に一つのテキスト、途中10分休憩して、後半に別のテキストと、毎回2つのテキストが平行して読み解かれていきます。
「片野家」の古文書は、岐阜県最南端、木曽三川の流れるところ、海津郡輪之内町というところ、文字通り輪中の地帯で、代々大庄屋勤めていました。記録は元治元年(1864)に書かれています。名のごとく、正月から始まって、晦日まで、勝手方の行事の1つ1つを克明に記録してあります。正月には何をどのように食べ、召使には何を遣わすか、年賀には何時行くか、何を携えるかなどです。
案に相違して、皆さん楽しそうに読み解き、子供の頃のお話や、年寄りから聞いた話なども出て、そういうことも私には興味深いものです。そういうお話を聞いていると、今お見かけしたところでは町に住み、学校の先生らしき方、どこかの奥様らしき方なども、草深い田舎で、野山を走り回り、麦の多い飯を食べ、ドンド焼を楽しんだガキ坊主だったことが伺えます。
古文書といっても、年代は幅広く、文書も武士の手になるものから、庄屋や商家、学者のもの、楷書やくずし字など、様々で、間口が広く、奥が深いと思うことしきりです。その文字を見ていると書いた人の書き癖のようなものがわかり、内容と照らし合わせ、どのような思いで書いたのかと想像する楽しみがあります。7月8月は古文書読解講習会のため、この研究会も夏休みになりましたが、9月の再開が待たれます。もちろん、読解講習会にも今年も3ヵ所出席する予定です。学ぶことが嬉しい時です。
『ひぐらし記』No.15 2007.7.15 福田美津枝・発行 より転載
若きセールスマンの芋作り
息子と、彼の友人M君が、わが家の空き畑でさつま芋を作っています。蔓が伸びて、順調に育っていますが、草も負けずに育ち、今は草取りに追われているようです。 彼らは3年ほど前に、わが家の山の果樹園にりんごの木を植え、時々手入れをして育てていましたが、いっこうに実がならず残念がっていました。そこで、成果がもっと早く得られるものをと思ったのか、この春「オバサン、畑で何かを作りたい」とM君が相談して来ました。
「沖(と呼んでいる地名)の畑なら空いてるで、そこで作ったらいいやん、今から作るんなら、手間がかからんさつま芋なんかいいんやない」と答えると、彼らは早速その準備を始めました。家人はその話を聞いて、沖の畑をトラクターで起こしてやりました。
さつま芋の苗は叔母(義母の妹)が作るのをいつも分けて貰っているので、彼らも義母を連れて叔母の所に行き、50本ほど分けて貰ってきて、義母の指導のもとに鍬で畝を立て、苗を挿していきました。その後、晴天ばかり続いたので、苗がつくかどうか心配していましたが、何とか9割ほどが根を張り、芽も伸びだしました。これに気を良くした彼らはもう2本畝を立て、どこかで新品種とかの苗を買ってきて、挿したようで、そこには品種名を書いたラベルが立ててありました。
ところで、これまで彼らと書いてきましたが、実際は、息子はM君に引きずられて嫌々やっていて、苗挿しを指導した義母は「M君は一生懸命やっているのに、あの子はなっちょらん、全然やる気がない」と怒っていました。休みの日にする手入れも、いつもM君に引っ張られています。M君は一人で草引きに来ていることもあり、時々息子に「福ちゃん、オジサンにばっかりやらせんで、ちょっとは自分でもやらなあかん」などと小言を言っています。家人は時々枯れた苗を補充したり、草引きや水遣りをやって、時々畑でM君と一緒に仕事をしているようです。
M君はセカンドカーに軽トラックを持っていて(彼の家は農業はないのに)、休みの日はそれに乗って畑にきます。畑仕事が終わるとうちに来て、それがお昼時や夕飯時であれば、家族と一緒にご飯を食べて、殺風景なわが家の食卓を賑わしてくれます。
そんな時のある日、「M君は百姓家に生まれたわけでもないに、何でこんな畑仕事をするん」と聞いたら「なんか、自分で作ったという実感を持ちたかったんです。たまたま福ちゃんちが百姓やってるんで、ここでならりんごを作れると思ったんやけど、りんごが成らんで、他に何か作りたいなと思って」そして「僕ら自動車売っているやないですか、そやけど僕が一生懸命売らんでも、車が欲しいと思ったらお客は買いに来て売れていく。そやけど畑仕事は僕がやってやらんとさつまいもも育たん、ああ自分でやっているっちゅう実感があるんです」びっくりびっくり。M君曰く「福ちゃんはこうも土地持っとるのにやりたがらん、小さい時からずっと田植えや稲刈り手伝わされて嫌になったと言っとった。僕にしてみればうらやましい限りです」。
 息子によれば、M君はトヨタ車販売会社の営業所でも実績1,2を争うセールスマンなのです。その彼が、物を作る実感を得たいと言って畑仕事をする。30歳の若者が、成績優秀のセールスマンの彼が、土に触れ、土の中から確かなものを作る手ごたえを求めている。嬉しいのか、感心したのかなんとも言えない感情が湧いてきました。
息子によれば、M君はトヨタ車販売会社の営業所でも実績1,2を争うセールスマンなのです。その彼が、物を作る実感を得たいと言って畑仕事をする。30歳の若者が、成績優秀のセールスマンの彼が、土に触れ、土の中から確かなものを作る手ごたえを求めている。嬉しいのか、感心したのかなんとも言えない感情が湧いてきました。
「オバサン、さつま芋が採れたらどうしよう、食いきれんよ」と言うので、「M君のトラックに積んで売りに歩くか、焼き芋屋でも始めようか」などと戯れています。それまでには休み毎の草引きが続きます。今は、若きセールスマンの芋つくりが楽しみ事の1つとなっています。
『ひぐらし記』No.15 2007.7.15 福田美津枝・発行 より転載
「沖(と呼んでいる地名)の畑なら空いてるで、そこで作ったらいいやん、今から作るんなら、手間がかからんさつま芋なんかいいんやない」と答えると、彼らは早速その準備を始めました。家人はその話を聞いて、沖の畑をトラクターで起こしてやりました。
さつま芋の苗は叔母(義母の妹)が作るのをいつも分けて貰っているので、彼らも義母を連れて叔母の所に行き、50本ほど分けて貰ってきて、義母の指導のもとに鍬で畝を立て、苗を挿していきました。その後、晴天ばかり続いたので、苗がつくかどうか心配していましたが、何とか9割ほどが根を張り、芽も伸びだしました。これに気を良くした彼らはもう2本畝を立て、どこかで新品種とかの苗を買ってきて、挿したようで、そこには品種名を書いたラベルが立ててありました。
ところで、これまで彼らと書いてきましたが、実際は、息子はM君に引きずられて嫌々やっていて、苗挿しを指導した義母は「M君は一生懸命やっているのに、あの子はなっちょらん、全然やる気がない」と怒っていました。休みの日にする手入れも、いつもM君に引っ張られています。M君は一人で草引きに来ていることもあり、時々息子に「福ちゃん、オジサンにばっかりやらせんで、ちょっとは自分でもやらなあかん」などと小言を言っています。家人は時々枯れた苗を補充したり、草引きや水遣りをやって、時々畑でM君と一緒に仕事をしているようです。
M君はセカンドカーに軽トラックを持っていて(彼の家は農業はないのに)、休みの日はそれに乗って畑にきます。畑仕事が終わるとうちに来て、それがお昼時や夕飯時であれば、家族と一緒にご飯を食べて、殺風景なわが家の食卓を賑わしてくれます。
そんな時のある日、「M君は百姓家に生まれたわけでもないに、何でこんな畑仕事をするん」と聞いたら「なんか、自分で作ったという実感を持ちたかったんです。たまたま福ちゃんちが百姓やってるんで、ここでならりんごを作れると思ったんやけど、りんごが成らんで、他に何か作りたいなと思って」そして「僕ら自動車売っているやないですか、そやけど僕が一生懸命売らんでも、車が欲しいと思ったらお客は買いに来て売れていく。そやけど畑仕事は僕がやってやらんとさつまいもも育たん、ああ自分でやっているっちゅう実感があるんです」びっくりびっくり。M君曰く「福ちゃんはこうも土地持っとるのにやりたがらん、小さい時からずっと田植えや稲刈り手伝わされて嫌になったと言っとった。僕にしてみればうらやましい限りです」。
「オバサン、さつま芋が採れたらどうしよう、食いきれんよ」と言うので、「M君のトラックに積んで売りに歩くか、焼き芋屋でも始めようか」などと戯れています。それまでには休み毎の草引きが続きます。今は、若きセールスマンの芋つくりが楽しみ事の1つとなっています。
『ひぐらし記』No.15 2007.7.15 福田美津枝・発行 より転載
ブログ内検索
最新記事
(07/30)
(07/08)
(06/20)
(06/06)
(05/28)
(04/16)
(02/25)
(01/18)
(12/30)
(12/14)
(11/10)
(10/27)
(10/16)
(10/07)
(10/01)
(09/22)
(09/11)
(07/12)
(06/25)
(06/04)
(05/27)
(05/14)
(04/24)
(04/16)
(03/31)
