農・人・くらし
NPO法人 農と人とくらし研究センター コラム
年齢
今、もっとも有名な農家は、おそらく青森県弘前市の木村秋則という人でしょう。書店に行くと彼の本が数種類、一番目立つところに平積みされています。
そう、『奇跡のりんご』のあの木村さんです。完全無農薬のりんご栽培に成功して、一躍有名人となった人です。
で、この項のタイトルがなぜ「年齢」なのかというと、先日、彼のことをとりあげたテレビ番組を観て、「ええーっ、それはないでしょう?」と思ったからです。
内容自体は彼を絶賛するもので、別に文句をつけるところはありません。気になったのは、スタジオに居並んでいろいろコメントしたり、彼のりんごを試食したりするタレントや司会者たちが、「おじいさんのりんご、おいしい!」とか、「おじいさん、すごい!」とか「おじいさんの優しさの詰まった味がする!」とか、とにかくやたら「おじいさん」を連発したことです。
彼は今、60歳です。確かに歯がないので(無農薬に切り替えて9年、まったくりんごがならず、生活費のために様々な仕事をしたそうで、キャバレーの呼び込みをしていた時に酔っぱらいに殴られて歯を折ったそうです)老けて見えます。でも、スタジオのみんなは彼の年齢を知っているわけで、「いまどき、60歳でおじいさんはないだろうヨ」と61歳の私は勝手に怒っているのです。本人はきっと平気だろうけど・・。
だって、60歳で「おじいさん」なら61歳の私は正真正銘、立派な[おばあさん]ですよ。別に、いいけど、サ。
なお、彼の栽培する「奇跡のりんご」は全国の有名レストランのシェフたちに引っ張りだこだそうで、我々の口にはとても入りません。スーパーで、一山いくらの安売りりんごを買って、農薬の味を噛みしめています。
そう、『奇跡のりんご』のあの木村さんです。完全無農薬のりんご栽培に成功して、一躍有名人となった人です。
で、この項のタイトルがなぜ「年齢」なのかというと、先日、彼のことをとりあげたテレビ番組を観て、「ええーっ、それはないでしょう?」と思ったからです。
内容自体は彼を絶賛するもので、別に文句をつけるところはありません。気になったのは、スタジオに居並んでいろいろコメントしたり、彼のりんごを試食したりするタレントや司会者たちが、「おじいさんのりんご、おいしい!」とか、「おじいさん、すごい!」とか「おじいさんの優しさの詰まった味がする!」とか、とにかくやたら「おじいさん」を連発したことです。
彼は今、60歳です。確かに歯がないので(無農薬に切り替えて9年、まったくりんごがならず、生活費のために様々な仕事をしたそうで、キャバレーの呼び込みをしていた時に酔っぱらいに殴られて歯を折ったそうです)老けて見えます。でも、スタジオのみんなは彼の年齢を知っているわけで、「いまどき、60歳でおじいさんはないだろうヨ」と61歳の私は勝手に怒っているのです。本人はきっと平気だろうけど・・。
だって、60歳で「おじいさん」なら61歳の私は正真正銘、立派な[おばあさん]ですよ。別に、いいけど、サ。
なお、彼の栽培する「奇跡のりんご」は全国の有名レストランのシェフたちに引っ張りだこだそうで、我々の口にはとても入りません。スーパーで、一山いくらの安売りりんごを買って、農薬の味を噛みしめています。
渡辺ひろ子(元・酪農家)
『私信 づれづれ草』NO.23(2010.2.28発行)より転載
『私信 づれづれ草』NO.23(2010.2.28発行)より転載
PR
あわくら通信読者様
「あわくら」を離れて5年が経ちました。
私たち夫婦共、年なりの健康を保って、思いのままくらせたという限りにおいては、この5年間、平穏な日々であったと思っています。
あわくらの15年を「むら私論」として整理する日課は、カタツムリの歩みですが続けております。
自らが傘寿を迎えると、高齢者問題は切実な課題として目の前を去来します。昨年から、近所の高齢者同士の集まりを持ったりしております。この様な中で「あわくら」での高齢者にかかわる小さな試みの部分を小冊子にしました。
高齢者自らが行動を起こすことの難しさの呟きです。
まえがき
私は、1989年11月から2005年3月までの15年4ヶ月を岡山の山村「あわくら」でくらしました。このむらで米を作り、野菜を育て、それを食べるという自給自足のくらし、そしてむらとの付き合いをしてきました。
田舎くらしでは、日々のくらしの中で地域との付き合いを大事にしなければなりません。農作物を作って食べるという百姓のくらしは、快適なものです。そして、一歩、外に目を向けるとむらの様々なくらしがあります。この、むらの様々なくらしのあり様が田舎くらしなのです。
私は、田舎くらしをする中で、私自身が「被験者」として実験材料となり、そして、また観察者としてくらしたようで、その体験を「あわくら通信」として発行してきました。
今、埼玉の「江南」でくらすようになって、あわくら16年の被験者としての体験を「むら私論 第1部」として記録し、あわくら通信(第14~32号)として発行しました。
このなかで、「限界集落」といわれる高齢者むらにくらして、高齢者のあり様を、体験の中での一つとして試みた事項を纏めた章(あわくら通信第23~26)を小冊子にしました。
この体験は、このむらにくらす被験者にとっての実証材料です。その内側にいて自らの問題として、高齢高齢者としてどうくらすか、高齢高齢者にとっては、1年1年がどのようなものであるか、厳しい現実があります。
私が関わり、お付き合いした方々は、5年後の今日、今おられるのは御二人だけで、夫々、高齢者施設でくらしておられます。私自身が、高齢高齢者の1人になって1年1年をどう生きるか、残された年月を考えるようになっております。
2010年2月 小松展之
小松展之『これからの「むら」への試み』(2010年3月30日発行)から
私たち夫婦共、年なりの健康を保って、思いのままくらせたという限りにおいては、この5年間、平穏な日々であったと思っています。
あわくらの15年を「むら私論」として整理する日課は、カタツムリの歩みですが続けております。
自らが傘寿を迎えると、高齢者問題は切実な課題として目の前を去来します。昨年から、近所の高齢者同士の集まりを持ったりしております。この様な中で「あわくら」での高齢者にかかわる小さな試みの部分を小冊子にしました。
高齢者自らが行動を起こすことの難しさの呟きです。
江南にて 小松展之
まえがき
私は、1989年11月から2005年3月までの15年4ヶ月を岡山の山村「あわくら」でくらしました。このむらで米を作り、野菜を育て、それを食べるという自給自足のくらし、そしてむらとの付き合いをしてきました。
田舎くらしでは、日々のくらしの中で地域との付き合いを大事にしなければなりません。農作物を作って食べるという百姓のくらしは、快適なものです。そして、一歩、外に目を向けるとむらの様々なくらしがあります。この、むらの様々なくらしのあり様が田舎くらしなのです。
私は、田舎くらしをする中で、私自身が「被験者」として実験材料となり、そして、また観察者としてくらしたようで、その体験を「あわくら通信」として発行してきました。
今、埼玉の「江南」でくらすようになって、あわくら16年の被験者としての体験を「むら私論 第1部」として記録し、あわくら通信(第14~32号)として発行しました。
このなかで、「限界集落」といわれる高齢者むらにくらして、高齢者のあり様を、体験の中での一つとして試みた事項を纏めた章(あわくら通信第23~26)を小冊子にしました。
この体験は、このむらにくらす被験者にとっての実証材料です。その内側にいて自らの問題として、高齢高齢者としてどうくらすか、高齢高齢者にとっては、1年1年がどのようなものであるか、厳しい現実があります。
私が関わり、お付き合いした方々は、5年後の今日、今おられるのは御二人だけで、夫々、高齢者施設でくらしておられます。私自身が、高齢高齢者の1人になって1年1年をどう生きるか、残された年月を考えるようになっております。
2010年2月 小松展之
小松展之『これからの「むら」への試み』(2010年3月30日発行)から
皆、百姓
熊本大学教授の徳野貞雄という人の著書『農村(ムラ)の幸せ、都会(マチ)の幸せ』を読んでいます。始まりの部分が特に面白いです。
「日本人は皆、百姓の小倅だった」
日本は稲作が作った国で、昭和30年代まで、みんな農山漁村で暮らしていた。人口の9割は百姓だった。暮らしの中身もほとんど変化なく、明治や江戸時代どころか、室町・鎌倉の時代までつながる暮らしのにおいを持っていた。高度経済成長がその暮らしを急激に変えた。
というのが、まあ大まかな中身です。面白いのは「高度経済成長期以前の暮らしを経験している者は室町時代にタイムスリップしても生きていける」というところです。
自給のためのいろいろな野菜を植え、漬物も自分の家で漬け、食事も自分の家で作り、かまどで薪を燃やしてご飯を炊き、掃除はほうきとはたき、洗濯はタライ。共同の水汲み場で洗い物。正月やお盆の行事、こままわしやたこあげなどの遊びも室町時代に定着したそうで、そんな暮らし方は本当に私の子ども時代そのものです。なるほど、私も室町時代にタイムスリップしても生きていけそうです。
高度成長期以降に生まれた世代との暮らし方の違いは、もう、「違い」というより「断絶」と呼ぶべきものでしょう。
徳野氏はこう書いています。
「現在ともっとも大きく違うのは、私達のご先祖様はいつも飢えていたということです。だから食べ物を探すことに必死でした」
高度成長期という、ほんの数年を境にまったく別の世界に移行してしまった日本人。「飢え」から「飽食」へ、突然の移行でした。
飢えを知らない世代に食べ物の大切さを教えるのは難しいでしょう。土のにおいを知らない人たちに自然の重さを実感させるのは難しいでしょう。
彼らは「環境に優しい暮らし」を考える時CO2を出さないエネルギー生産を求めます。
室町時代人間の我々はエネルギーの使用量を減らす暮らしを考えます。「昔の暮らしに逆戻りは出来ない」と言う人もいるけれど、江戸時代くらいまで暮らし方を逆戻ししても、人間、そんなに不幸にはならないように思います。医学の進歩で、長生き出来るようになったけど、長生きが不幸な場合もいっぱいあるわけで、まあ、そこそこの暮らしをして、そこそこで死ぬってのも、悪くないと思うのでありまして、「生きることの意味」なんて考える暇もなく食うためにのみ働いて、ぱったり死ぬ、そういう生き物に立ち戻ろうよ。
と、徳野氏の著書の主旨とは関係なく、後ろ向きな提案をする渡辺であります。
『農村の幸せ・都会の幸せ』
徳野貞雄・著
生活人新書
740円十税
なお、私が書店でこの本をぱらぱらめくって、買う気になったのは、最後の方に、わが家の近くで合鴨農法をやっている「進 利行」さんが登場していたからです。
「農業・農村のニューモデル」の項に「中核兼業農家」として、進さんが紹介されています。彼は消防署に勤めながら農業をやっていて、私はよく「この人は道楽で百姓やってます」なんてからかったりしていました。もう消防署は退職して、正真正銘の百姓です。酒飲みで、よく勉強会だか飲み会だかを開いていますが私を誘ってはくれません。
渡辺ひろ子(元・酪農家)
『私信 づれづれ草』NO.23(2010.2.28発行)より転載
「日本人は皆、百姓の小倅だった」
日本は稲作が作った国で、昭和30年代まで、みんな農山漁村で暮らしていた。人口の9割は百姓だった。暮らしの中身もほとんど変化なく、明治や江戸時代どころか、室町・鎌倉の時代までつながる暮らしのにおいを持っていた。高度経済成長がその暮らしを急激に変えた。
というのが、まあ大まかな中身です。面白いのは「高度経済成長期以前の暮らしを経験している者は室町時代にタイムスリップしても生きていける」というところです。
自給のためのいろいろな野菜を植え、漬物も自分の家で漬け、食事も自分の家で作り、かまどで薪を燃やしてご飯を炊き、掃除はほうきとはたき、洗濯はタライ。共同の水汲み場で洗い物。正月やお盆の行事、こままわしやたこあげなどの遊びも室町時代に定着したそうで、そんな暮らし方は本当に私の子ども時代そのものです。なるほど、私も室町時代にタイムスリップしても生きていけそうです。
高度成長期以降に生まれた世代との暮らし方の違いは、もう、「違い」というより「断絶」と呼ぶべきものでしょう。
徳野氏はこう書いています。
「現在ともっとも大きく違うのは、私達のご先祖様はいつも飢えていたということです。だから食べ物を探すことに必死でした」
高度成長期という、ほんの数年を境にまったく別の世界に移行してしまった日本人。「飢え」から「飽食」へ、突然の移行でした。
飢えを知らない世代に食べ物の大切さを教えるのは難しいでしょう。土のにおいを知らない人たちに自然の重さを実感させるのは難しいでしょう。
彼らは「環境に優しい暮らし」を考える時CO2を出さないエネルギー生産を求めます。
室町時代人間の我々はエネルギーの使用量を減らす暮らしを考えます。「昔の暮らしに逆戻りは出来ない」と言う人もいるけれど、江戸時代くらいまで暮らし方を逆戻ししても、人間、そんなに不幸にはならないように思います。医学の進歩で、長生き出来るようになったけど、長生きが不幸な場合もいっぱいあるわけで、まあ、そこそこの暮らしをして、そこそこで死ぬってのも、悪くないと思うのでありまして、「生きることの意味」なんて考える暇もなく食うためにのみ働いて、ぱったり死ぬ、そういう生き物に立ち戻ろうよ。
と、徳野氏の著書の主旨とは関係なく、後ろ向きな提案をする渡辺であります。
『農村の幸せ・都会の幸せ』
徳野貞雄・著
生活人新書
740円十税
「農業・農村のニューモデル」の項に「中核兼業農家」として、進さんが紹介されています。彼は消防署に勤めながら農業をやっていて、私はよく「この人は道楽で百姓やってます」なんてからかったりしていました。もう消防署は退職して、正真正銘の百姓です。酒飲みで、よく勉強会だか飲み会だかを開いていますが私を誘ってはくれません。
渡辺ひろ子(元・酪農家)
『私信 づれづれ草』NO.23(2010.2.28発行)より転載
徴農制
ちょっと前、テレビの「太田総理」(お笑いコンビ「爆笑問題」が司会をして、タレントや政治家などがその日のテーマ・・太田光本人の提案が多いが、たまに他の出演者が提案する場合もある・・について論議し、最後に賛否の投票をする。視聴者も電話投票で意志表示できる、という番組)で、俳優の辰巳琢郎が「徴農制」を提案しました。
「若者に一定期間(一年くらい)強制的に農業体験をさせることによって、農業の大変さ、大切さ、汗を流して働くことの喜びなどを実感させる。そうすれば、食べ物のありがたさ、農業の大切さがわかるだろう。そして、彼らの中から、農業を生涯の仕事にしたいと思う若者も出てきて、農業後継者不足問題も解決できるだろう。」
というのが、辰巳さんの提案理由でした。賛否は半々で、論議が始まりました。政治家も賛否に分かれ、自民党若手議員は「農業の将来は農業者自ら考えることで、ビジネス努力で新しい道を開拓し成功している個人や企業もある。例えば、中国の富裕層に向けて、良質なものを生産し、高価な値段で売って利益を上げている、というように。だから、日本の農業の将来は暗いばかりじゃない」
農業者も二人出ていて賛否に分かれました。小学生などの農業体験の教育的効果をあげ、まず子どもたちに農業や自然を知る機会を作ってやることが日本の農業を救うことにもつながる、という賛成派。そして、反対派の高齢の農家の人は「農業の後継者がいないのは、農業で食えないからだ。農業体験して、将来農業をやりたいという若者がたくさん出てきても、食えないじゃぁ仕方ない。農業が食える仕事になることがまず始まりだろう」と主張していました。
最終的に、確か一票差で「可決」となって番組は終わりました。
 う~ん、私は、う~ん、ちょっと反対に近いかなぁ。子どもたちに農業体験をさせることは大切だと思うし、それは、今各地で試みられているような、「田植えと稲刈り」とか「芋ほり」とかだけじゃなく、土つくりから収穫後の後始末・来年への準備に至る全過程を体験するものであってほしいと思います。
う~ん、私は、う~ん、ちょっと反対に近いかなぁ。子どもたちに農業体験をさせることは大切だと思うし、それは、今各地で試みられているような、「田植えと稲刈り」とか「芋ほり」とかだけじゃなく、土つくりから収穫後の後始末・来年への準備に至る全過程を体験するものであってほしいと思います。
しかし、それを農家に来てやられると、仕事の邪魔でしかないし、第一、今どきの子どもの扱いとか、モンスターペアレントの扱いとか、そんなの農家で背負いきれる範疇を越えているわけで、一年で農家の大半が精神科に通院することになるかも・・。
本来、教育は教育機関がやるべきことで、でも、今の学校にこれ以上を望むのも酷だと思います。今でも教師の多くが精神科に通院もしくは入院している現実があるわけで・・。
学校のカリキュラムを大幅に変更して、数学とか英語とか科学とかの時間を減らして、農業を正式な科目として入れればいいと思います。
この国はもう「右肩上がり」の成長は戻って来ない「老成期」に入ったのだから、難解な数学や物理式を解ける能力より、何か起きても生きていける智恵や能力、そして他人とやさしい関係を作りそれを持続するこころを育てることに、教育の力点を移すべきだと思います。
子どもの学力が世界ランキングで韓国に負けた!なんて騒いで、「学校」のケツをひっぱたいてみてもしょうがないよ。
今までとは違う国になる、そしてそれは「進化」なのだと思うこと。
太田総理! 農業再生も、教育再生もここから始めよう、というのが渡辺ひろ子のマニフェストです、いかがでしょう。
な~んて、ここでほざいてもオヨビデナイ。
渡辺ひろ子(元・酪農家)
『私信 づれづれ草』NO.24(2010.3.28発行)より転載
「若者に一定期間(一年くらい)強制的に農業体験をさせることによって、農業の大変さ、大切さ、汗を流して働くことの喜びなどを実感させる。そうすれば、食べ物のありがたさ、農業の大切さがわかるだろう。そして、彼らの中から、農業を生涯の仕事にしたいと思う若者も出てきて、農業後継者不足問題も解決できるだろう。」
というのが、辰巳さんの提案理由でした。賛否は半々で、論議が始まりました。政治家も賛否に分かれ、自民党若手議員は「農業の将来は農業者自ら考えることで、ビジネス努力で新しい道を開拓し成功している個人や企業もある。例えば、中国の富裕層に向けて、良質なものを生産し、高価な値段で売って利益を上げている、というように。だから、日本の農業の将来は暗いばかりじゃない」
農業者も二人出ていて賛否に分かれました。小学生などの農業体験の教育的効果をあげ、まず子どもたちに農業や自然を知る機会を作ってやることが日本の農業を救うことにもつながる、という賛成派。そして、反対派の高齢の農家の人は「農業の後継者がいないのは、農業で食えないからだ。農業体験して、将来農業をやりたいという若者がたくさん出てきても、食えないじゃぁ仕方ない。農業が食える仕事になることがまず始まりだろう」と主張していました。
最終的に、確か一票差で「可決」となって番組は終わりました。
しかし、それを農家に来てやられると、仕事の邪魔でしかないし、第一、今どきの子どもの扱いとか、モンスターペアレントの扱いとか、そんなの農家で背負いきれる範疇を越えているわけで、一年で農家の大半が精神科に通院することになるかも・・。
本来、教育は教育機関がやるべきことで、でも、今の学校にこれ以上を望むのも酷だと思います。今でも教師の多くが精神科に通院もしくは入院している現実があるわけで・・。
学校のカリキュラムを大幅に変更して、数学とか英語とか科学とかの時間を減らして、農業を正式な科目として入れればいいと思います。
この国はもう「右肩上がり」の成長は戻って来ない「老成期」に入ったのだから、難解な数学や物理式を解ける能力より、何か起きても生きていける智恵や能力、そして他人とやさしい関係を作りそれを持続するこころを育てることに、教育の力点を移すべきだと思います。
子どもの学力が世界ランキングで韓国に負けた!なんて騒いで、「学校」のケツをひっぱたいてみてもしょうがないよ。
今までとは違う国になる、そしてそれは「進化」なのだと思うこと。
太田総理! 農業再生も、教育再生もここから始めよう、というのが渡辺ひろ子のマニフェストです、いかがでしょう。
な~んて、ここでほざいてもオヨビデナイ。
渡辺ひろ子(元・酪農家)
『私信 づれづれ草』NO.24(2010.3.28発行)より転載
獣害
私がパートに行ってるY牧場の牧草地にシカとイノシシが出てきます。シカは牧草の柔らかいのを食べます。だから、草が伸びて硬くなるとあまり出て来ません。でも、イノシシの方はずーっと毎日出て来ます。夫婦に子どもが4頭。イノシシは牧草を食うわけではなく、土中のミミズを食うために出て来るのです。だから、土を掘ります。ひたすら掘ります。まるでトラクターで鋤いたようになります。もちろん牧草はダメになります。その面積が日に日に増えて行きます。ワナを仕掛けてもなかなか入ってくれないし、あきらめ顔のYさんです。
ものの本によると、イノシシの農作物被害はひとが農耕を始めた大昔からのことだそうです。あきらめるしかないのでしょう。
ところで、新聞でちょっと衝撃的なニュースを読みました。
アフリカのどこかの野生動物保護区で、シマウマが増えすぎて農作物に深刻な被害が出ているそうで、その解決策として、シマウマの一部をライオンなどの肉食獣の保護区に追い込む、つまり、ライオンの狩りの対象にすることで「駆除」するという方法を選んだというのです。
まあ、合理的といえば言えるだろうし、自然界の本来の姿に戻したとも言えるだろうけど、でも、今までライオンのいない環境で生まれ育って生きてきたシマウマがいきなりライオンの群れに遭遇したら・・と思うと何だか痛ましいです。ひとと動物たちとの関係はいろいろ難しいですね。特に、ひとには経済ってものが付いてまわるので一層難しくなります。イノシシたちはミミズがたくさんいる所を探しているだけなんだけどね。
渡辺ひろ子(元・酪農家)
『私信 づれづれ草』NO.24(2010.3.28発行)より転載
ものの本によると、イノシシの農作物被害はひとが農耕を始めた大昔からのことだそうです。あきらめるしかないのでしょう。
ところで、新聞でちょっと衝撃的なニュースを読みました。
アフリカのどこかの野生動物保護区で、シマウマが増えすぎて農作物に深刻な被害が出ているそうで、その解決策として、シマウマの一部をライオンなどの肉食獣の保護区に追い込む、つまり、ライオンの狩りの対象にすることで「駆除」するという方法を選んだというのです。
まあ、合理的といえば言えるだろうし、自然界の本来の姿に戻したとも言えるだろうけど、でも、今までライオンのいない環境で生まれ育って生きてきたシマウマがいきなりライオンの群れに遭遇したら・・と思うと何だか痛ましいです。ひとと動物たちとの関係はいろいろ難しいですね。特に、ひとには経済ってものが付いてまわるので一層難しくなります。イノシシたちはミミズがたくさんいる所を探しているだけなんだけどね。
渡辺ひろ子(元・酪農家)
『私信 づれづれ草』NO.24(2010.3.28発行)より転載
むらのつきあい(1990.2)
「むら」は永代の付き合いが、くらしの基盤ですが、これがだんだん難しくなるのかなと思います。
わが大字には20戸あって、当主が60才以上の家が11戸、50才以下が3戸、若者在住1戸という具合です。20戸の家の殆どの後継者、あるいは次の後継者(孫)は、ふる里を知らないで育っているわけです。
むらに生まれ育ってこそ「ふる里」と考えると、10~20年という期間を単位としてみると「むら」は根幹から様変わりするように思います。「むら」の維持に従来と違った基準が必要になりそうです。(あわくら通信第2号)
小松展之
『むらのくらしからみえること』(2009年4月15日発行)から
農作業暦から生まれたもの
昨年秋から始まった「伊深」を様々な視点から考える活動で、どこからでも出てくる話は、「田んぼも畑も荒れていくなあ」という言葉です。このような活動に携わる委員が、70~80代の男の人が多いこともあります。伊深ばかりではなく、どこの地域も同じようなものですが、荒れた田畑を増やさないようにすることくらいは、私たちでできることではないかと、まだうら若き女たちは立ち上がりました。
休耕田に菜の花やれんげの花で、ずっと前の里の風景を作ることもその一手ですが、もっと積極的に田畑を利用してもらうように、田畑での野菜づくりを進めることにしました。団塊の世代のリタイア問題をマスコミなどは扱っていますが、それは男の問題としているのに対し、農村ではパート勤めをリタイアした女性も、次の仕事を探っています。そこに着目して、野菜づくりに引き込む作戦です。自分の食べ物は自分の手で作るようにと。
今の時代、女は姑から物を教わりたくないのです。そこには古めかしい、嫁とはこうあるべきなどという教訓が必ず含まれているからです。姑に替わる野菜づくりの参考書を作ろうと、地域の姑世代から、現代の野菜づくりの方法を聞き取りしました。
さすがに他人には教訓めいた話は出ませんでしたが、その代わりに、昔のいろいろな野良仕事の方法、それにまつわる行事の様子などが次々出てきました。それはとても興味深く、この地域だけにあることや、その人の暮らしのありようや人生を思わせるものなど、ぜひこのことを記録しておきたいと思いました。
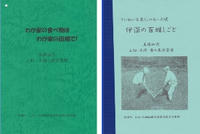 それで、農作業暦「わが家の食べ物はわが家の田畑で~美濃加茂上切・大洞の農作業暦」と併せて、「ていねいな暮らしのあった頃 伊深の百姓仕事~美濃加茂上切・大洞昔の農作業暦」の2冊を、3月に発刊しました。
それで、農作業暦「わが家の食べ物はわが家の田畑で~美濃加茂上切・大洞の農作業暦」と併せて、「ていねいな暮らしのあった頃 伊深の百姓仕事~美濃加茂上切・大洞昔の農作業暦」の2冊を、3月に発刊しました。
現代版の暦「わが家の・・・」は、月ごとのカレンダー方式にして、余白を十分取り、メモを書きいれ、10年後には自分の暦としていただくように。昔の暦「伊深の百姓仕事・・・」は、読んで保存していただくようにとしました。
今後は、この現代版暦を使って、「野菜づくり講座」として地域の休耕田で実習する講座を開くつもりです。また、「百姓仕事」のほうは、これからも聞き取りを続けて、書き足す改訂版を次々に出していこうと思っています。
こんなことで、休耕田対策が解決するとは到底思えませんが、「田んぼも畑も荒れる」「若いもんは百姓もやらん」と嘆くだけよりは、話のタネにもなるし、とりわけ、当人たちが次々に夢や行動を広げて、楽しんでいるのですから、よほどいいと思います。
福田美津枝
※ 上記で紹介したものは、希望される方にお分けします。農と人とくらし研究センターnouhito@rircl.jpへご連絡ください。郵送料210円で送ります。
休耕田に菜の花やれんげの花で、ずっと前の里の風景を作ることもその一手ですが、もっと積極的に田畑を利用してもらうように、田畑での野菜づくりを進めることにしました。団塊の世代のリタイア問題をマスコミなどは扱っていますが、それは男の問題としているのに対し、農村ではパート勤めをリタイアした女性も、次の仕事を探っています。そこに着目して、野菜づくりに引き込む作戦です。自分の食べ物は自分の手で作るようにと。
今の時代、女は姑から物を教わりたくないのです。そこには古めかしい、嫁とはこうあるべきなどという教訓が必ず含まれているからです。姑に替わる野菜づくりの参考書を作ろうと、地域の姑世代から、現代の野菜づくりの方法を聞き取りしました。
さすがに他人には教訓めいた話は出ませんでしたが、その代わりに、昔のいろいろな野良仕事の方法、それにまつわる行事の様子などが次々出てきました。それはとても興味深く、この地域だけにあることや、その人の暮らしのありようや人生を思わせるものなど、ぜひこのことを記録しておきたいと思いました。
現代版の暦「わが家の・・・」は、月ごとのカレンダー方式にして、余白を十分取り、メモを書きいれ、10年後には自分の暦としていただくように。昔の暦「伊深の百姓仕事・・・」は、読んで保存していただくようにとしました。
今後は、この現代版暦を使って、「野菜づくり講座」として地域の休耕田で実習する講座を開くつもりです。また、「百姓仕事」のほうは、これからも聞き取りを続けて、書き足す改訂版を次々に出していこうと思っています。
こんなことで、休耕田対策が解決するとは到底思えませんが、「田んぼも畑も荒れる」「若いもんは百姓もやらん」と嘆くだけよりは、話のタネにもなるし、とりわけ、当人たちが次々に夢や行動を広げて、楽しんでいるのですから、よほどいいと思います。
福田美津枝
※ 上記で紹介したものは、希望される方にお分けします。農と人とくらし研究センターnouhito@rircl.jpへご連絡ください。郵送料210円で送ります。
◆わが家の食べ物はわが家の田畑で~美濃加茂上切・大洞の農作業暦(A4版 12枚)
◆ていねいな暮らしのあった頃 伊深の百姓仕事~美濃加茂上切・大洞昔の農作業暦(A4版 28ページ)
次の項目をご記入の上、ご連絡ください。
1.郵便番号2.住所
3.氏名
4.メールアドレス
5.ご希望の農作業暦及び部数
「わが家の食べ物はわが家の田畑で~美濃加茂上切・大洞の農作業暦」 _部
「ていねいな暮らしのあった頃 伊深の百姓仕事~美濃加茂上切・大洞昔の農作業暦」 _部
尚、ご希望部数によりまして、郵送料が変わることがあります。ご了承ください。
ブログ内検索
最新記事
(07/30)
(07/08)
(06/20)
(06/06)
(05/28)
(04/16)
(02/25)
(01/18)
(12/30)
(12/14)
(11/10)
(10/27)
(10/16)
(10/07)
(10/01)
(09/22)
(09/11)
(07/12)
(06/25)
(06/04)
(05/27)
(05/14)
(04/24)
(04/16)
(03/31)
