農・人・くらし
NPO法人 農と人とくらし研究センター コラム
「気違い農政周游紀行⑨」苦労の味
私はこの4月、ろくに知識も経験もないのに、行きがかり上、コメ作りに挑戦することになった。苦労して荒廃農地を開墾したばかりだったので、目の前で新たな耕作放棄地が生まれるのが、いたたまれなかったのである。4枚合わせても1反ほどの面積だが、除ケ入と呼ばれる棚田で、ただ一人田んぼをつくり続けていた玉蔵さんが今年はもうできないと言っていると聞き、あわててお借りして続ける算段をした。50枚を数える棚田のうち、今もかつての姿をとどめているのはこの4枚だけである。播種期の直前で、あわてて農協に苗を注文した。ちょっと標高が高いのが心配だったが「あきたこまち」を植えた。玉蔵さんがつくっていた「ゆめしなの」は種の確保が間に合わなかったからである。
多くの仲間の手を借りて、区民農園として取り組んだ。だから「うちでとれたコメ」というのは正確ではない。代かきは農業委員の護さん、水の心配は家が近い正純さん、稲作の経験のある人が中心となった。田植えには、地域の子ども育成会の親子も参加して50人近く集まった。除草剤を使いたくないと言った手前、草取りは私の仕事となった。
夏場、子山羊を連れ出して木陰に繋ぎ、鳥の声を聴きながら、回りに誰一人いない田んぼで過す時間はぜいたくなものだった。しかし、泥の中で足をとられながら前かがみの姿勢での作業は、想像以上に身体こたえた。田の草取りをしながら、戦前の小作制度の理不尽さを想った。こんな苦労をして、収穫の半分も地主に取られたら、たまらないと実感した。
田んぼを借りに行ったとき、玉蔵さんは、参考にと、貯水池の水位を記録した5枚のコピーを手渡してくれた。5年分の折れ線グラフは、夏場の水の苦労を示していた。しかし、今年は水不足の心配もなく、思いのほか順調に育って収穫の時期をむかえた。
8月末に、用事でしばらく留守にしていて家に戻ると、田んぼが大変なことになっているとの一報が入った。急いで行ってみると、収穫間際の稲が倒されている。イノシシの仕業だった。今までの苦労はなんだったのかと、やるせなさが募った。田んぼを快く貸してくれた玉蔵さんに申し訳ないと思った。
あわてて田の水を抜き、人に頼んで獣道にワナも仕掛けた。イノシシの襲来は4日で止まった。ワナにはイノシシではなくカモシカがかかったが、逃がしてやったという。
稲刈りとハザかけ、それに脱穀は、主だった区民農園のメンバーの男衆だけで済ませた。収量は、期待した半分にも満たなかった。12月を前に、倒れた稲と切り株が残る田んぼを、来年のために、もう一度耕起して、一年目のコメ作りの作業はすべて終了した。
振り返れば気苦労ばかり多かった。今、そのコメを食べながら、苦労の味を噛みしめている。おいしくないわけがない。
片倉和人
PR
「農村生活」時評30 "いま山村から撤退か"
大した開発地ではないが、わが住まいは首都圏内の都市近郊地域の一部だと思っていた。この頃、あたりの様子が少し変って来た。近くに空き家もあるがそれだけでなく、生活圏内の商店がどんどん変わる。自動車販売店やGスタンドのほかに手作りパン屋さんが閉店し、私が定期購読雑誌を頼んでいた本屋さんがつぶれて購読そのものを止めてしまった。これらの店はどれも建物はそのままなので、まわりが淋しくなり、残された空間が殺風景である。なかでも郵便ポストのあったコンビニがやっと高齢者向きになったのに、営業不振で突然無くなったのには驚いたし、いかにも不便になった。一方車で行く数キロ範囲には東と西に巨大な商業店舗群ができているらしいが、別に用事がないので行ったことが無い。全国的な地域の変容と衰退は地理的条件も歴史的条件も様々だが、決して他人事ではない。首都圏におけるかつての集合住宅団地のオールドタウン化が伝えられているが、その次に来るのは私の住むような開発団地のケースである。
 日本中の地域が壊れてしまい、その典型として「限界集落」問題が社会的な課題となって久しいが、ある新聞に若手研究者の提言として過疎集落の"積極的な"「撤退農村計画」が登場したのには驚いた。私は10年前に「集落移転後の20年」という小冊子を書いたから、ほぼ30年前の"消極的"・計画的な山村集落のふもとへの集団移転計画とその後の住民生活を論じたという立場がある。その調査事例の片方については移転計画時にも関わったので、気持ちの中には住民の転居はあれで良かったのかという反省の念もあった。
日本中の地域が壊れてしまい、その典型として「限界集落」問題が社会的な課題となって久しいが、ある新聞に若手研究者の提言として過疎集落の"積極的な"「撤退農村計画」が登場したのには驚いた。私は10年前に「集落移転後の20年」という小冊子を書いたから、ほぼ30年前の"消極的"・計画的な山村集落のふもとへの集団移転計画とその後の住民生活を論じたという立場がある。その調査事例の片方については移転計画時にも関わったので、気持ちの中には住民の転居はあれで良かったのかという反省の念もあった。
この若い研究者グループの善意を疑うものではないが、多分、現代的な割り切りに優れているのだろう。国土計画論者の中にはカネのかかる山村は全部撤退して都市を集中的に整備すべし、という意見があるそうだ。なるほど、そういってもらったほうが問題の局面がはっきりする。日本の山々はみんな、何らかの形で水源だから、その水流は連続して上から下まで全部、大小のダムにしてその水で、整備される都市に日本人は皆、生活することにするか。
ダムといえば昨今、やっと論議の対象、行政の検討課題になったが、私にはすでに日本中がダムで埋め尽くされたような気分である。半世紀前、学生時代に当時、花形だった天竜川の佐久間ダム建設現場を見学したことがあり、それが今は土砂で埋まり、下流に害があるなどと聞くと、幼さがよみがえり苦い思いがする。このダム論議を逆手に取り、あるところで"山村は人材のダムだ"、"日本文化のダムだ"とやりかえしたこともある。
ダムに限らないが、日本という国のありかたが政治経済的にあるいは社会的に問われる時代になった。そこで維持経費問題で山村地域から住民を撤退させるプランが堂々と提示されるなら、単に限界集落論的範囲ではなく、原理的な国土問題として21世紀列島プランを根本的に国民的討議する必要がある。いま行われているような耳障りの良い、一見経済上合理的に見える、改革論者による短時間の討議で、これ以上山村や地域社会が壊されてはこまる。今はここ20年、30年来、年数と経費をかけてきたいわゆる「都市」も粗末な工事であちこちが崩れてきている事態を迎えているのである。
そんな折、小田切徳美先生の最新刊、「農山村再生」(岩波ブックレット・№768)を読んでやっと安心した。この本の提起の根本は新しいコミュニティだから、そこに学ぶべき課題は多々あるが、それは今後の宿題にしたい。ここで先生の再生提案に悪乗りしてこれからの農山村について考えるならば、撤退ではなく、まずいま住民の住んでいる地域の暮らし保全であり、その上で肉親の帰郷もふくむ様々な縁による新住民の移住プランが基本である。そもそも人がいなければ農林業振興はできないし、主として山村から成る列島の骨組みを形成する地域の環境保全もできない。
その際の論点の一つはこの地域の自然環境が日本人の現在持っている財産であり、これからも多くの価値を生む可能性があることを認めるか、否定するかである。もう一つは日本に農業はいらないのか、農と結びついている林業はいらないのか、農とむすびついている沿岸漁業はいらないのかという問題である。さらに大都市整備を集中的に実施して五輪でもやろうかというのと、農山村の暮らしを保障して、自給も互助システムもある落ち着いた住民生活をつくるのとが、国民経済上どちらが安上がりか、その環境負荷如何ということである。
これは本当は科学的にキチンと計算したほうがいいかもしれない。しかし、問題は計画論的な技術課題ではなく、あるところで菅直人国家戦略相がいったように、"政治的判断を政治的に検討する"という政治課題なのである。
積極的撤退論のポイントは表からは隠れているが農のあり方をめぐる考え方、というか、棄農の勧めである。この提案者は合理的な農業振興策、農地保全も計画しているというが、いまの農山村民の身についた農業技術、山村保全技術なくして、個性に満ちた傾斜地などは簡単には再生、活用はできない。本当に地域を再生するというなら、この人たち自身を保全する、そこでくらしが成り立つように手筈を整えるほかない。それは当事者にとって中々困難な暮らしだろう。しかし私が移転経過を調べて痛感することは、通勤・通学する世代は別として、山村民にとって農や山と離れた移転先の平地に、高齢者の幸福はないのである。
森川辰夫
この若い研究者グループの善意を疑うものではないが、多分、現代的な割り切りに優れているのだろう。国土計画論者の中にはカネのかかる山村は全部撤退して都市を集中的に整備すべし、という意見があるそうだ。なるほど、そういってもらったほうが問題の局面がはっきりする。日本の山々はみんな、何らかの形で水源だから、その水流は連続して上から下まで全部、大小のダムにしてその水で、整備される都市に日本人は皆、生活することにするか。
ダムといえば昨今、やっと論議の対象、行政の検討課題になったが、私にはすでに日本中がダムで埋め尽くされたような気分である。半世紀前、学生時代に当時、花形だった天竜川の佐久間ダム建設現場を見学したことがあり、それが今は土砂で埋まり、下流に害があるなどと聞くと、幼さがよみがえり苦い思いがする。このダム論議を逆手に取り、あるところで"山村は人材のダムだ"、"日本文化のダムだ"とやりかえしたこともある。
ダムに限らないが、日本という国のありかたが政治経済的にあるいは社会的に問われる時代になった。そこで維持経費問題で山村地域から住民を撤退させるプランが堂々と提示されるなら、単に限界集落論的範囲ではなく、原理的な国土問題として21世紀列島プランを根本的に国民的討議する必要がある。いま行われているような耳障りの良い、一見経済上合理的に見える、改革論者による短時間の討議で、これ以上山村や地域社会が壊されてはこまる。今はここ20年、30年来、年数と経費をかけてきたいわゆる「都市」も粗末な工事であちこちが崩れてきている事態を迎えているのである。
そんな折、小田切徳美先生の最新刊、「農山村再生」(岩波ブックレット・№768)を読んでやっと安心した。この本の提起の根本は新しいコミュニティだから、そこに学ぶべき課題は多々あるが、それは今後の宿題にしたい。ここで先生の再生提案に悪乗りしてこれからの農山村について考えるならば、撤退ではなく、まずいま住民の住んでいる地域の暮らし保全であり、その上で肉親の帰郷もふくむ様々な縁による新住民の移住プランが基本である。そもそも人がいなければ農林業振興はできないし、主として山村から成る列島の骨組みを形成する地域の環境保全もできない。
その際の論点の一つはこの地域の自然環境が日本人の現在持っている財産であり、これからも多くの価値を生む可能性があることを認めるか、否定するかである。もう一つは日本に農業はいらないのか、農と結びついている林業はいらないのか、農とむすびついている沿岸漁業はいらないのかという問題である。さらに大都市整備を集中的に実施して五輪でもやろうかというのと、農山村の暮らしを保障して、自給も互助システムもある落ち着いた住民生活をつくるのとが、国民経済上どちらが安上がりか、その環境負荷如何ということである。
これは本当は科学的にキチンと計算したほうがいいかもしれない。しかし、問題は計画論的な技術課題ではなく、あるところで菅直人国家戦略相がいったように、"政治的判断を政治的に検討する"という政治課題なのである。
積極的撤退論のポイントは表からは隠れているが農のあり方をめぐる考え方、というか、棄農の勧めである。この提案者は合理的な農業振興策、農地保全も計画しているというが、いまの農山村民の身についた農業技術、山村保全技術なくして、個性に満ちた傾斜地などは簡単には再生、活用はできない。本当に地域を再生するというなら、この人たち自身を保全する、そこでくらしが成り立つように手筈を整えるほかない。それは当事者にとって中々困難な暮らしだろう。しかし私が移転経過を調べて痛感することは、通勤・通学する世代は別として、山村民にとって農や山と離れた移転先の平地に、高齢者の幸福はないのである。
森川辰夫
鳥日記 (2009.10)
で、先日、バイトの休みの日に次女と車で出かけました。
和白干潟に私はまだ行ったことがありませんでした。で、和白にわりと近くに住む友人真紀ちゃんに案内を頼みました。
車を近くに乗り入れることが出来ない地理にあり、重いカメラバッグを下げて少し歩きました。とてもいい天気で、汗をかきかき歩いてやっと干潟に下りることは出来ました。
でも、遠くにカモやアオサギやカモメがいて、その中のどれがミヤコドリか、私には判別出来ません。きょろきょろしていると、突然、8~9羽の黒っぽい鳥がぱたぱたと海の中道の方へ飛んで行きました。
「今のがミヤコドリだったと思おう」ということにして、急に潮が満ちてきた干潟を後にしました。
海の中道から志賀島を一周しました。志賀島は金印が出土したといわれる所です。岩場にウミウに混じってクロサギもいました。クロサギを見るのも初めてです。(ウミウと思っていたら、写真を見て、鳥プロ三丸さんが、「これはクロサギ」)
和白から2日後、こんどは、三丸さんのお誘いで中津市の八面山に「ハイタカの渡り」を見に行きました。ハイタカは今の時期、朝鮮半島から越冬のために九州・四国などに渡って来るのだそうです。「希少生物研究会」の主要メンバーである三丸さんは特に鷲鷹大好きなので、「渡り」の時期にはほとんど毎日、八面山の山頂で双眼鏡覗いて、数を数えてノートに書き込んで一日を過ごしています。
北風の日がいい、ということだったけど、この日は穏やかで無風だったので3羽しか見られませんでしたが、写真も何とか撮れました。
ジョウビタキもたくさん帰ってきたし、カモやカモメも増えて、鳥好きにはいい季節になって来ました。犬の散歩コースの雑木林にもいろんな鳥がいてたのしみです。ところが、ここを宅地造成するとかで、地鎮祭がありました。ええっ、この林をつぶしてしまうの? こんなところ宅地で売り出したって家を建てて住む人いないだろうに・・。牛舎のすぐ横だもの。臭いし、ハエは多いし。でも、鳥はいっぱいすんでいるんだよ。
渡辺ひろ子(元・酪農家)『私信 づれづれ草』NO.20(2009.10.31発行)より転載
冬(12~2月)
冬になったというもう一つに荒神祭りがある。このむらの収穫祭である。今は12月の第1日曜日、朝から神社の掃除、祭りの準備をして、午後当家に集まり当家を開き、神社で祭礼、公会堂で直らい(懇親会)というこのむらの出事で冬が始まる。
1989年12月から1990年2月は、このむらでくらし始めた、初めての冬であった。午前の外気温が氷点下8度にもなり、家の硝子戸の結露が凍り、氷の結晶の花が咲き、陽の光にダイヤモンドダストが輝くのをみて驚かされ、深々と降り積もる雪というなかで、家の片付け、屋敷周りの整備、木屋(穀物倉庫、農具置場、車庫、仕事場)建築準備で終わった。
野良は、たまねぎ苗の植え付け、大根、白菜など秋野菜の収穫貯蔵など冬越しに備える。大根など根菜は畑に深く埋めるのが普通の冬越しであるが、畑のまま籾殻を深く被せておくと凍結に耐えるとともに未成熟の大根は冬の間も保温が効いて生長して越冬大根になる。
こうして野良が終わる。昔は、杉檜の枝打ち、炭焼など冬の山仕事の始まりであったが、今は殆んど誰も山に入らず、一二の人が機械による枝打ちをして終日エンジンの音が響くくらいである。
年末に、妻久枝の出番であるクリスマス、歳暮の贈物の用意が始まる。フルーツケーキつくり、餅つきである。春から造ってきた伽羅ぶき、山椒の実の佃煮、梅干、奈良漬それに岡山の特産であるママカリの酢漬け、アミの塩辛これらをセットにして、「1年の元気」の挨拶として友人たちに贈る。これらが無事に終わって年が越せるのである。
山の初雪は12月である。時としては50㎝も積もることもあるが本格的な積雪は、年明けから2月中旬の間である。一夜にして30~50㎝もの雪が積もり、終日降り続くこともある。幸いにして、公道は、村がグレイダーで除雪してくれるので雪の中でも自動車で出掛けることができる。しかし、40㎝も積もると、除雪に半日も掛かり、小中学校が休校になることが何度かある。
問題は、玄関から公道までと家の周囲の雪掻きである。朝1番の仕事となり、1日に何回も雪掻きをすることもある。高齢者世帯では、大変な重労働である。
山の冬を感じるのは、山が鳴ることと、黒く見える杉檜の山肌を真横に降る雪である。深々と降る雪もあるが、真横の降る雪の荒々しさは、山のエネルギーを感じさせる。
こうして、冬篭りが始まる。1月は何かと正月に絡んだ行事で終わるが、春からの稲作の記録の整理と次年の生産計画、野菜の生産記録の整理と春野菜生産計画から始まって「あわくら通信」の記事と編集、農業の青色申告・所得税確定申告が冬篭りの中での仕事である。
妻久枝は、収集してきた古布を選び分けしながらのパッチワークで冬を越す。
2月も半ばを過ぎると、急に春めいた陽射しを感じるようになる。今までの沈んだような灰色の空気が急に明るくなる日が来る。しかし、その翌日は30㎝も40㎝もの雪が降ることもある。この様な激しい天気の変わりの中に春を感じるのである。気がつくと山の裾の林の中に満作が黄色な可憐な花をひっそりと咲かせており、田んぼの畦に蕗の薹を見るようになる。
こうして、野良のことが何となく気になり、気忙しくなって冬が終わるのである。
小松展之『あわくら通信』第34号(2008.5.21発行)より転載
田んぼ事情
私は田んぼ全部を人に作ってもらっていて、だから、人の米作りについてとやかくいう資格はないのだけれど・・と思いつつ、でも気になっていることがあるのです。
ここ2~3年、周辺の田んぼの様子が変です。ヒエがびっしりと生え茂って稲が見えないくらいの田がそこかしこに見受けられます。しかも、年々増えて来てます。稲刈りまで、そのままです。
決して「無農薬栽培」が増えたというようなことではないと思います。
普通、田植えの時に、除草剤を入れます。水管理をうまくやれば、一度の除草剤でほぼ大丈夫です。少しは草が生えます。以前はそれを「田の草取り」といって、腰を曲げて手で取っていました。
最近は、田に這いつくばって草取りする人の姿はほとんど見かけません。除草剤の効能がアップしたせいもあるし、「少々の草には目をつぶる」人が増えたこともあるのでしょう。
でも、本当にここ2~3年のことですが、「少々の草」なんて次元ではないヒエだらけの田があちこちに出現して、年々増殖しつつあります。
いったい何が原因なのでしょう。
じつは、うちの隣のMさんの田がうちのすぐ前にあります。おじいさんは先年亡くなって、おばあさん一人暮らしです。86歳です。田畑の管理は隣町に住む息子さん(60歳)が来てやっています。去年も田はヒエだらけになり、稲刈り前になって、おばあさんが稲より高く伸びたヒエを鎌で刈り取りました。何日も何日もかけて。
でも、その時はすでにヒエは実って種を落としてしまっていたのです。だから、今年もヒエびっしり。そして今年も稲刈り直前におばあさんが鎌でやっぱりヒエを刈りました。
おばあさんがヒエを刈る理由は「めんどうしいから」です。「めんどうしい」とは「恥ずかしい」という方言です。60歳の息子さんにとって、ヒエだらけの田は別に「恥」でもないのでしょう。
どうやらこのあたりに、ヒエ田増殖の秘密がありそうです。
米を一生懸命作ってきた「お百姓さん」たちが死んだり、動けなくなったりして、しかし、次の世代は「ずっとサラリーマン」だったわけで、米作りの技術も精神もうまく伝達出来ていないままなのではないかと思うのです。「ヒエを生やしていたらめんどうしい」と思って、せっせと田の草取りをしてきた先人たちは、老いて「腰の曲がった老人」になりました。そのことを思うと、今、後継者たちが、ヒエを取らないことを安直に批判することも出来ません。
「ヒエ取りして、米が少しくらい多く出来ても、それでなんぼ儲かるってもんでもなし」という声に答えられる人がいるでしょうか。
ただ、何千年もの間、連綿と伝えられてきた「百姓の心」が途絶えていくことに、無念の思いが残るのです。
渡辺ひろ子(元・酪農家)『私信 づれづれ草』NO.20(2009.10.31発行)より転載
ひまわり・コスモス
中津市のある地区では、営農組合が「日本一の面積のコスモス畑をめざす」と言っていると新聞に出ていました。
基盤整備した立派な水田が花畑です。それはそれで美しいし楽しいけれど、その一方で、「海外に企業が資本を投入して、食料生産を」となると、ええーっ?と、思いませんか?
国内の農地に無為に花を咲かせて、食料生産は海外で。変な話でしょ。
農民は、もっと怒れよ!
渡辺ひろ子(元・酪農家)『私信 づれづれ草』NO.19(2009.9.25発行)より転載
鳥日記 (2009.9)
どこを見てもサギばかりの季節はまだ続いています。
先日、基地前の池にバンでもいないかなぁと出かけました。池の道路側の端で双眼鏡で池を見ていると、一台の車がやって来てすぐそばに止まりました。ドアがあいて、若い男が降りて来ました。見ると、迷彩服の上下。ちょっとぎょっとしました。
男は近づいてきます。
私の位置から池をはさんで丁度基地が正面に見えます。まるで基地を双眼鏡でのぞいているような状態です。あやしいおばさんです。
ヤバッ。不審者と思われて様子を見に自衛隊員が来たに違いない。
と、一瞬思いました。
迷彩服の男はなおも近づいてきます。そして、「何か見えますか?」と言うので、「鳥です。バンがいないかと思って来てみたけど、いないみたいです」と、何だか言い訳してるみたいだなあと思いながら答えました。
「ああ、鳥ですか。僕は雷魚を釣りに来たんですが、水草が茂っていて釣りは無理みたいですね」と言って、車に戻って走り去りました。
自衛隊ではなかったようです。まぎらわしい服装するなよ。
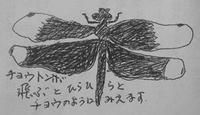 池には、ほていあおいがびっしりと茂っており、水色の花が一面に咲いていました。
池には、ほていあおいがびっしりと茂っており、水色の花が一面に咲いていました。
バンはいなかったけど、チョウトンボがたくさん飛んでいました。
鳥は。サギだけ。
渡辺ひろ子(元・酪農家)『私信 づれづれ草』NO.19(2009.9.25発行)より転載
先日、基地前の池にバンでもいないかなぁと出かけました。池の道路側の端で双眼鏡で池を見ていると、一台の車がやって来てすぐそばに止まりました。ドアがあいて、若い男が降りて来ました。見ると、迷彩服の上下。ちょっとぎょっとしました。
男は近づいてきます。
私の位置から池をはさんで丁度基地が正面に見えます。まるで基地を双眼鏡でのぞいているような状態です。あやしいおばさんです。
ヤバッ。不審者と思われて様子を見に自衛隊員が来たに違いない。
と、一瞬思いました。
迷彩服の男はなおも近づいてきます。そして、「何か見えますか?」と言うので、「鳥です。バンがいないかと思って来てみたけど、いないみたいです」と、何だか言い訳してるみたいだなあと思いながら答えました。
「ああ、鳥ですか。僕は雷魚を釣りに来たんですが、水草が茂っていて釣りは無理みたいですね」と言って、車に戻って走り去りました。
自衛隊ではなかったようです。まぎらわしい服装するなよ。
バンはいなかったけど、チョウトンボがたくさん飛んでいました。
鳥は。サギだけ。
渡辺ひろ子(元・酪農家)『私信 づれづれ草』NO.19(2009.9.25発行)より転載
ブルガリアの酪農
ブルガリアといえばヨーグルトしか思いつかないくらい、酪農の国というイメージです。そのブルガリアの酪農が壊滅の危機に瀕しているといいます。EU(ヨーロッパ連合)問題です。
EU加盟を果たしたブルガリア。当然、農産物にもEU基準が課せられます。酪農の国ブルガリアは酪農の歴史が長いだけに、中小規模の古い酪農家が多く、乳牛の飼養方法も設備も旧式なのだそうです。
しかし、EUの基準は厳しく、それをクリアするのは、ほとんどの農家には無理だというのです。EU基準を満たすために設備投資をしなくてはならない。補助金を受けるには「完全放牧」が条件であり、舎飼いでやってきた多くの農家は対象外となる。自己資金を用意出来る農家はとても少ない。
というようなことなのです。
食べるものの品質や生産方法の基準を厳しくするのは当然であるのだけれど、厳しくし過ぎて、結果として生産者を苦しめ、廃業に追い込んで行くと、単に仕事だけでなく、地域やそこで暮らす人々の文化までも壊してしまうことにならないかと思うのです。
大きな企業が潤沢な資金で大規模に生産する農産物が市場を席巻する社会がいいか、小さな農家が穀物も野菜も畜産も小規模に生産し、農家同士が助け合いながら、地域の行事や環境保全も農業生産の一環として、「日常」としてやって行くというのがいいか、選択の余地はもうないのでしょうか。
これは、ブルガリアの問題というより、「農業」と「産業」との関係の問題として、きわめて世界的であり、かつ我がムラ的でもあります。
渡辺ひろ子(元・酪農家)『私信 づれづれ草』NO.19(2009.9.25発行)より転載
EU加盟を果たしたブルガリア。当然、農産物にもEU基準が課せられます。酪農の国ブルガリアは酪農の歴史が長いだけに、中小規模の古い酪農家が多く、乳牛の飼養方法も設備も旧式なのだそうです。
しかし、EUの基準は厳しく、それをクリアするのは、ほとんどの農家には無理だというのです。EU基準を満たすために設備投資をしなくてはならない。補助金を受けるには「完全放牧」が条件であり、舎飼いでやってきた多くの農家は対象外となる。自己資金を用意出来る農家はとても少ない。
というようなことなのです。
食べるものの品質や生産方法の基準を厳しくするのは当然であるのだけれど、厳しくし過ぎて、結果として生産者を苦しめ、廃業に追い込んで行くと、単に仕事だけでなく、地域やそこで暮らす人々の文化までも壊してしまうことにならないかと思うのです。
大きな企業が潤沢な資金で大規模に生産する農産物が市場を席巻する社会がいいか、小さな農家が穀物も野菜も畜産も小規模に生産し、農家同士が助け合いながら、地域の行事や環境保全も農業生産の一環として、「日常」としてやって行くというのがいいか、選択の余地はもうないのでしょうか。
これは、ブルガリアの問題というより、「農業」と「産業」との関係の問題として、きわめて世界的であり、かつ我がムラ的でもあります。
渡辺ひろ子(元・酪農家)『私信 づれづれ草』NO.19(2009.9.25発行)より転載
ブログ内検索
最新記事
(07/30)
(07/08)
(06/20)
(06/06)
(05/28)
(04/16)
(02/25)
(01/18)
(12/30)
(12/14)
(11/10)
(10/27)
(10/16)
(10/07)
(10/01)
(09/22)
(09/11)
(07/12)
(06/25)
(06/04)
(05/27)
(05/14)
(04/24)
(04/16)
(03/31)
