農・人・くらし
NPO法人 農と人とくらし研究センター コラム
カテゴリー「■ くらし」の記事一覧
- 2025.11.05
[PR]
- 2007.12.04
内戦の地にも人々の暮らしがある(中)
- 2007.12.04
内戦の地にも人々の暮らしがある(上)
内戦の地にも人々の暮らしがある(中)
JICA(国際協力機構)の研修生を初めて岡谷の農と人とくらし研究センターに迎えて「構想づくりワークショップ」と銘打った3日間の研修を行った(2007年10月18日~20日)。(社)農山漁村女性・生活活動支援協会がJICAから委託を受けて実施する「農村女性能力向上」コースの研修生で、生活改善アプローチを日本で学んで帰国後に自国で取り組むことを目標としている。今年は、カメルーン、チャド、ニジェール、タンザニア、イエメン、アフガニスタン、インド、スリランカ、フィジー、メキシコの10カ国から11人(女性9人、男性2人)が参加していた。
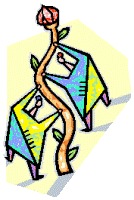 農村開発にたずさわる研修生たちに考えてもらいたかったのは、将来についてのビジョンをもつことの大切さである。その日暮らしの貧しい人たちは、お金や仕事がないだけでなく、将来になんら夢や希望をもっていない場合が多い。そういう人たちに対して、お金や仕事を与える援助ではなく、将来について自分のビジョンをもつことを手助けするような支援ができないか、その方法を伝えたいと思った。
農村開発にたずさわる研修生たちに考えてもらいたかったのは、将来についてのビジョンをもつことの大切さである。その日暮らしの貧しい人たちは、お金や仕事がないだけでなく、将来になんら夢や希望をもっていない場合が多い。そういう人たちに対して、お金や仕事を与える援助ではなく、将来について自分のビジョンをもつことを手助けするような支援ができないか、その方法を伝えたいと思った。
「参加型農村調査から構想づくりへ」をテーマにしたワークショップのプログラムを用意した。1日目の午後は皆で地元の地区を歩いて生活環境点検を行い、宝(良い点)とチャレンジ(問題点)を探し、参加者自らデータを収集する。二つの班に分かれて、2日目はそれを地図に落し込み、課題と「モッタイナイ」資源をリストアップする。その上でこの地区の将来の構想図(ビジョン)を1枚の大きな紙に描く。3日目は、課題の解決もしくはビジョンの実現をはかるプロセスを考える。班ごとに1つのテーマを決め、女性グループを育成して課題にとりくむという筋書きの寸劇を作って演じる。
プログラムは順調に進み、研修生は笑顔で岡谷を後にした。思い通りに実施できたのは、多くの方の助けを借りてのことだった。環境点検の案内役をお願いした区長の山之内寛さん、ボランティアで参加いただいた諏訪農業改良普及センターの林邦子さん、岐阜県から馳せ参じてくださった福田美津枝さん、それに休みをとって手伝ってくれた姉と妻、3日間を通じて世話をやいてくれた父母、JICA研修コーディネーターの栗田理恵さん、農山漁村女性・生活活動支援協会の担当者兼講師の富澤ひとみさんと古田由美子さん、こうした方々が一つのチームとなって、ファシリテーター(進行役)の私を支えてくれた。
ワークショップの最後は、短くてもふりかえりの時間をとって、参加者全員に感想を述べてもらうことにしている。岡谷での3日間をふりかえり、「将来に対して明るいイメージをもつことが大切だとわかった」と研修生のひとりが感想を述べた。そう語ったのは、最年少の20代男性、アフガニスタンからの研修生のバリさんだった。ビジョンを持つことの大切さを伝えたいと思ったが、ビジョンの中身は人それぞれで、内容まで特に深く考えていなかった。「明るい」という形容詞が、私の心に小さな棘のように引っかかった。
片倉和人
「参加型農村調査から構想づくりへ」をテーマにしたワークショップのプログラムを用意した。1日目の午後は皆で地元の地区を歩いて生活環境点検を行い、宝(良い点)とチャレンジ(問題点)を探し、参加者自らデータを収集する。二つの班に分かれて、2日目はそれを地図に落し込み、課題と「モッタイナイ」資源をリストアップする。その上でこの地区の将来の構想図(ビジョン)を1枚の大きな紙に描く。3日目は、課題の解決もしくはビジョンの実現をはかるプロセスを考える。班ごとに1つのテーマを決め、女性グループを育成して課題にとりくむという筋書きの寸劇を作って演じる。
プログラムは順調に進み、研修生は笑顔で岡谷を後にした。思い通りに実施できたのは、多くの方の助けを借りてのことだった。環境点検の案内役をお願いした区長の山之内寛さん、ボランティアで参加いただいた諏訪農業改良普及センターの林邦子さん、岐阜県から馳せ参じてくださった福田美津枝さん、それに休みをとって手伝ってくれた姉と妻、3日間を通じて世話をやいてくれた父母、JICA研修コーディネーターの栗田理恵さん、農山漁村女性・生活活動支援協会の担当者兼講師の富澤ひとみさんと古田由美子さん、こうした方々が一つのチームとなって、ファシリテーター(進行役)の私を支えてくれた。
ワークショップの最後は、短くてもふりかえりの時間をとって、参加者全員に感想を述べてもらうことにしている。岡谷での3日間をふりかえり、「将来に対して明るいイメージをもつことが大切だとわかった」と研修生のひとりが感想を述べた。そう語ったのは、最年少の20代男性、アフガニスタンからの研修生のバリさんだった。ビジョンを持つことの大切さを伝えたいと思ったが、ビジョンの中身は人それぞれで、内容まで特に深く考えていなかった。「明るい」という形容詞が、私の心に小さな棘のように引っかかった。
片倉和人
PR
内戦の地にも人々の暮らしがある(上)
PARCスリランカ報告会に岡谷から駆けつけた。2007年10月5日、東京広尾のJICA地球ひろばにおいて、「スリランカ内戦の現状と今後の展望」と「ジャフナ漁村の人々の暮らしとプロジェクト報告」と題する講演があった。報告者は、アジア太平洋資料センター(PARC)共同代表の中村尚司さんと井上礼子さん。PARCは、少数民族タミル人の住むジャフナ半島で、漁村の人々の自立と持続的な発展を支援する民際協力を行っている。最近ジャフナを訪れた帰国報告だったが、2007年4月29日深夜、スリランカのコロンボに滞在していた中村さんは、LTTE(タミル・イーラム開放のトラ)空軍機によるコロンボ空襲をホテルの部屋から目撃したという。
井上さんの報告によれば、1980年代から続く内戦で、ジャフナ半島では、多数民族シンハラ人の政府軍による攻撃を受け、タミル人の漁民たちは家を失い難民となった。そうした難民たちが、2002年の停戦合意後、海岸に家を建てて生活の再建を始めていて、PARCは2004年5月にジャフナに事務所を設置して、彼らの生活支援に着手した。
 まず、乾燥魚加工を始めるべく、2004年12月インドネシアに乾燥魚技術研修に行く。その直後12月24日、スマトラ沖地震の津波が襲い、難民の家は跡形もなく流される。PARCは津波緊急援助で住宅の再建を支援、一日も早い漁の再開と従来の生活への復帰をめざす漁民に対して、地引網のための網と船を提供、被災した女性たちには乾燥魚加工の支援を開始する。しかし、2006年8月内戦が再燃、ジャフナは陸の孤島と化し、軍は漁民たちに漁も海岸に近づくことも禁止する。食糧にもことかく漁民に、PARCは紅茶、砂糖、スパイス、粉ミルク、さかな缶詰などを送る緊急食糧救援を行い、さらに漁に出られない彼らのために養鶏のプロジェクトを開始する。
まず、乾燥魚加工を始めるべく、2004年12月インドネシアに乾燥魚技術研修に行く。その直後12月24日、スマトラ沖地震の津波が襲い、難民の家は跡形もなく流される。PARCは津波緊急援助で住宅の再建を支援、一日も早い漁の再開と従来の生活への復帰をめざす漁民に対して、地引網のための網と船を提供、被災した女性たちには乾燥魚加工の支援を開始する。しかし、2006年8月内戦が再燃、ジャフナは陸の孤島と化し、軍は漁民たちに漁も海岸に近づくことも禁止する。食糧にもことかく漁民に、PARCは紅茶、砂糖、スパイス、粉ミルク、さかな缶詰などを送る緊急食糧救援を行い、さらに漁に出られない彼らのために養鶏のプロジェクトを開始する。
平和時の生活改善の取り組みしか知らない私には、PARCのプロジェクトの困難さは、ちょっと想像を越えていた。講演後の意見交換で、「平和構築を待っていられない。紛争地域でも、生活支援の取り組みを、できることはやる」と、スリランカと関わりの深い参加者のひとりが発言していた。内戦地域にも生活があり、そこには生活改善を必要とする人がいる。戦争状態だから、支援活動をしなくていい、という訳にはいかない。そういう趣旨の発言だった。
もっと詳しい話を聞きたいと思ったが、近々岡谷でJICA研修の受け入れを控えていて、準備の心配があったので、交流会には参加しないでその日は報告と意見交換だけ聞いて帰った。
片倉和人
井上さんの報告によれば、1980年代から続く内戦で、ジャフナ半島では、多数民族シンハラ人の政府軍による攻撃を受け、タミル人の漁民たちは家を失い難民となった。そうした難民たちが、2002年の停戦合意後、海岸に家を建てて生活の再建を始めていて、PARCは2004年5月にジャフナに事務所を設置して、彼らの生活支援に着手した。
平和時の生活改善の取り組みしか知らない私には、PARCのプロジェクトの困難さは、ちょっと想像を越えていた。講演後の意見交換で、「平和構築を待っていられない。紛争地域でも、生活支援の取り組みを、できることはやる」と、スリランカと関わりの深い参加者のひとりが発言していた。内戦地域にも生活があり、そこには生活改善を必要とする人がいる。戦争状態だから、支援活動をしなくていい、という訳にはいかない。そういう趣旨の発言だった。
もっと詳しい話を聞きたいと思ったが、近々岡谷でJICA研修の受け入れを控えていて、準備の心配があったので、交流会には参加しないでその日は報告と意見交換だけ聞いて帰った。
片倉和人
ブログ内検索
最新記事
(07/30)
(07/08)
(06/20)
(06/06)
(05/28)
(04/16)
(02/25)
(01/18)
(12/30)
(12/14)
(11/10)
(10/27)
(10/16)
(10/07)
(10/01)
(09/22)
(09/11)
(07/12)
(06/25)
(06/04)
(05/27)
(05/14)
(04/24)
(04/16)
(03/31)
